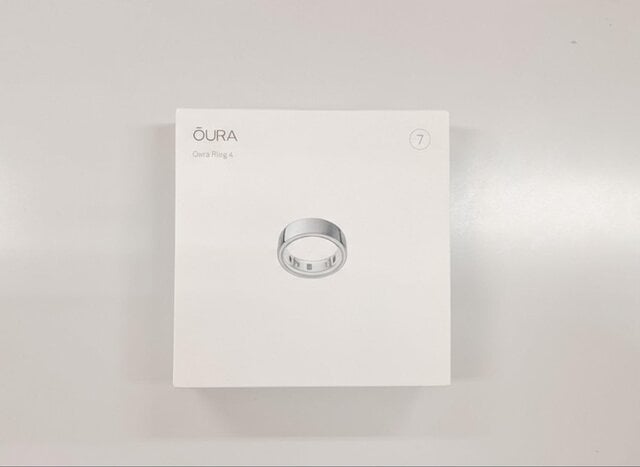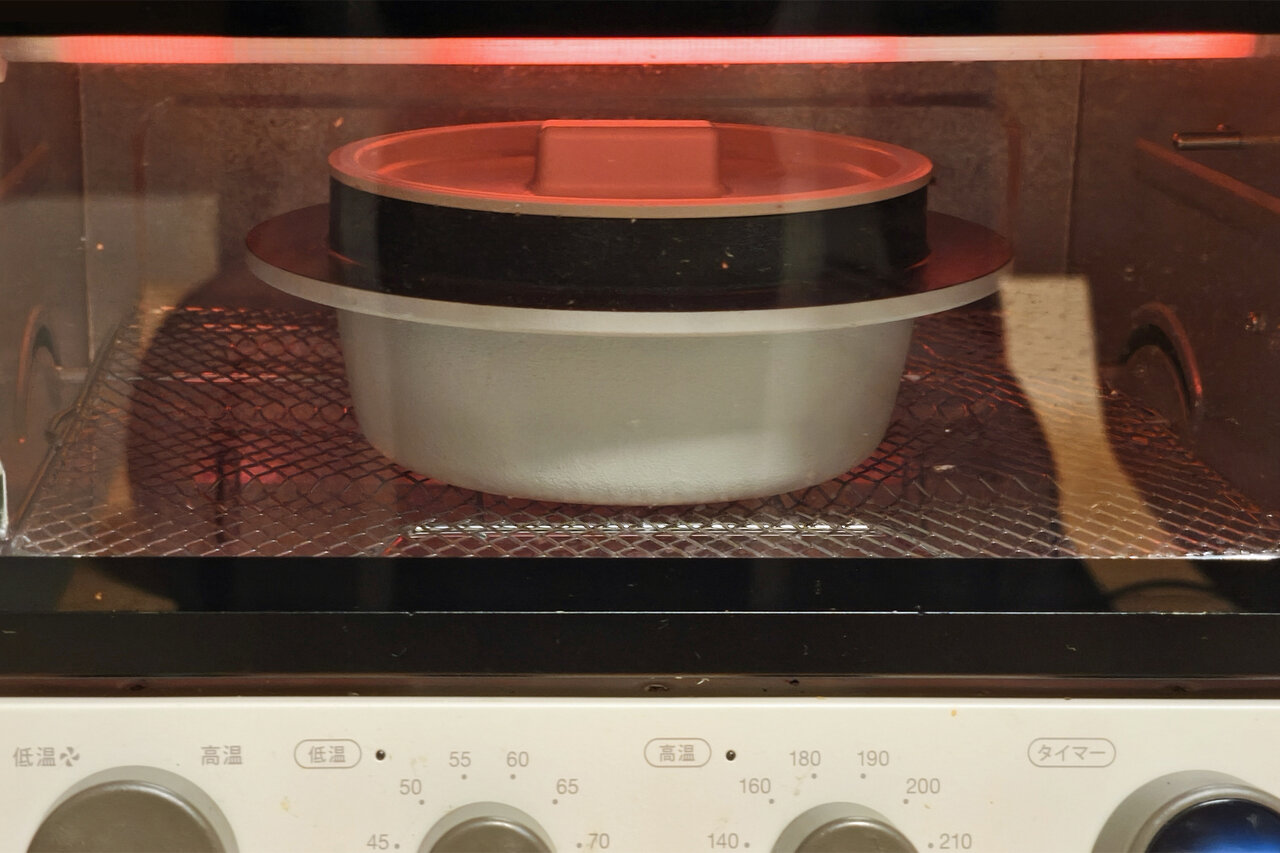家事の時短を叶える家電として、多くの家庭で活躍しているロボット掃除機。しかしいざ購入しようとすると、今や種類の多さや機能の豊富さに圧倒されてしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、家電エバンジェリストとして執筆のほかテレビなどにも出演する筆者が、あなたのライフスタイルにぴったりの一台を見つけるための「選び方ガイド」と、世界のロボット掃除機市場を牽引する主要メーカーの特徴を解説します。賢い選択で、快適な毎日を手に入れましょう!
この記事では、家電エバンジェリストとして執筆のほかテレビなどにも出演する筆者が、あなたのライフスタイルにぴったりの一台を見つけるための「選び方ガイド」と、世界のロボット掃除機市場を牽引する主要メーカーの特徴を解説します。賢い選択で、快適な毎日を手に入れましょう!
ロボット掃除機を選ぶ際に考慮すべきポイントとは?
ロボット掃除機を選ぶ際に考慮すべきポイントは多岐にわたります。以下の項目を上から順に確認するだけで、あなたのニーズに合った製品を見つけることができます。
置き場所と部屋の状況を把握する
ロボット掃除機を選ぶ上で、まず重要なのが設置場所と部屋の状況を把握することです。部屋の広さによって、必要な稼働時間やバッテリー容量が変わってきます。家具が多かったり、椅子がたくさんあったりと複雑な形状の部屋であれば、マッピング機能の精度が高いモデルを選ぶと良いでしょう。
またフローリング、カーペット、タイルなど、床の素材によって吸引力やブラシの種類、水拭き機能の有無などを考慮する必要があります。フローリングやタイルが多い場合、吸引と水拭きの両方に対応する2in1タイプが最適です。
カーペットの部屋がある場合は吸引力が強く、カーペットを検知すると自動的に吸引力を強化する「カーペットブースト機能」や、カーペット上で水拭きモップを持ち上げる「モップリフトアップ機能」などを搭載するモデルを選びましょう。毛足の長いカーペットは、ロボット掃除機の走行が困難になったり、絡まりやすい場合があるので注意が必要です。
またフローリング、カーペット、タイルなど、床の素材によって吸引力やブラシの種類、水拭き機能の有無などを考慮する必要があります。フローリングやタイルが多い場合、吸引と水拭きの両方に対応する2in1タイプが最適です。
カーペットの部屋がある場合は吸引力が強く、カーペットを検知すると自動的に吸引力を強化する「カーペットブースト機能」や、カーペット上で水拭きモップを持ち上げる「モップリフトアップ機能」などを搭載するモデルを選びましょう。毛足の長いカーペットは、ロボット掃除機の走行が困難になったり、絡まりやすい場合があるので注意が必要です。

カーペットの部屋がある場合は「カーペットブースト機能」や「モップリフトアップ機能」などを搭載するモデルを選ぶとよい
下に隙間がある家具がある場合は、ロボット掃除機が家具の下を潜り抜けられるか、掃除機の高さを確認しましょう。家具の下が掃除できると、ホコリがたまりにくくなります。
ロボット掃除機が巻き込みやすいコード類は事前にまとめるか、ロボット掃除機が検知・回避するセンサー性能を持つモデルを選ぶと安心です。
ロボット掃除機が巻き込みやすいコード類は事前にまとめるか、ロボット掃除機が検知・回避するセンサー性能を持つモデルを選ぶと安心です。
目的別で清掃方式を選ぼう
現在市販されているロボット掃除機は、単にゴミを吸い取るだけでなく、多様な清掃方式を搭載しています。
吸引のみ……日常のホコリ掃除に最適
最もシンプルなタイプで手軽に導入できます。日常的なホコリや髪の毛、小さなゴミの除去に特化しており、価格も比較的リーズナブルです。カーペットの部屋が多い、水拭きは自分で行っている、初期費用を抑えたい場合などに向いていますが、最近は水拭きもできる2in1タイプが主流で、吸引のみの製品は減っています。
水拭きのみ……フローリングの水拭き優先
吸引機能がなく、水拭きに特化したモデルです。フローリングのべたつきや軽い汚れを拭き取るのに向いています。既にスティックタイプの掃除機などを持っていて、水拭きの手間を省きたい家庭や、メインの床材がフローリングの家庭に向いています。
2in1タイプ……吸引+水拭き
1台で吸引と水拭きの両方を行えるタイプです。吸引と水拭きを同時に行えて清掃時間を短縮できる「同時作業タイプ」と、吸引後にモップを装着して水拭きを行う「別々作業タイプ」に分かれます。
同時作業タイプは、日常的に水拭き掃除を行いたい場合や、清掃時間をとにかく短縮したい、日常的な軽い汚れを効率よく掃除したい場合に向いています。別々作業タイプは、たまに水拭き掃除も行いたいというニーズに向いています。
吸引のみ……日常のホコリ掃除に最適
最もシンプルなタイプで手軽に導入できます。日常的なホコリや髪の毛、小さなゴミの除去に特化しており、価格も比較的リーズナブルです。カーペットの部屋が多い、水拭きは自分で行っている、初期費用を抑えたい場合などに向いていますが、最近は水拭きもできる2in1タイプが主流で、吸引のみの製品は減っています。
水拭きのみ……フローリングの水拭き優先
吸引機能がなく、水拭きに特化したモデルです。フローリングのべたつきや軽い汚れを拭き取るのに向いています。既にスティックタイプの掃除機などを持っていて、水拭きの手間を省きたい家庭や、メインの床材がフローリングの家庭に向いています。
2in1タイプ……吸引+水拭き
1台で吸引と水拭きの両方を行えるタイプです。吸引と水拭きを同時に行えて清掃時間を短縮できる「同時作業タイプ」と、吸引後にモップを装着して水拭きを行う「別々作業タイプ」に分かれます。
同時作業タイプは、日常的に水拭き掃除を行いたい場合や、清掃時間をとにかく短縮したい、日常的な軽い汚れを効率よく掃除したい場合に向いています。別々作業タイプは、たまに水拭き掃除も行いたいというニーズに向いています。
ゴミ収集機能の有無
清掃後のゴミ捨ての手間を省きたい場合は、充電ステーションに自動でゴミを収集する機能のあるものが便利です。自動ゴミ収集ステーションがあると、ロボット掃除機が充電ステーションに戻るたびに、本体のゴミを自動で収集ステーション内のダストボックスや紙パックに吸い上げてくれます。数週~数カ月間はゴミ捨てが不要になり、衛生的です。

清掃後のゴミ捨ての手間を省きたい場合は、自動ゴミ収集機能が便利
ゴミを自動で収集する場合は、紙パック式と、紙パックが不要なダストビン式に分かれます。
現在主流となっている紙パック式は、ゴミに直接触れずに捨てられるため衛生的で、ハウスダストやアレルギーを持つ人に向いています。ただし定期的な紙パックの交換が必要で、ランニングコストもかかります。
ダストビン式は、スティック掃除機のゴミ収集容器のイメージで、容器にゴミがたまるため、ランニングコストがかかりません。ただしゴミ捨て時にホコリが舞ったり、ゴミに直接触れる可能性があります。また定期的にダストビンを清掃するなどの手入れが必要です。
自動ゴミ収集機能がない場合は、掃除ごと、もしくは何回か掃除した後に本体のダストボックスを手動で空にする必要があります。本体のゴミを手動で捨てる代わりに、充電ステーションがコンパクトで済み、価格も抑えられます。
現在主流となっている紙パック式は、ゴミに直接触れずに捨てられるため衛生的で、ハウスダストやアレルギーを持つ人に向いています。ただし定期的な紙パックの交換が必要で、ランニングコストもかかります。
ダストビン式は、スティック掃除機のゴミ収集容器のイメージで、容器にゴミがたまるため、ランニングコストがかかりません。ただしゴミ捨て時にホコリが舞ったり、ゴミに直接触れる可能性があります。また定期的にダストビンを清掃するなどの手入れが必要です。
自動ゴミ収集機能がない場合は、掃除ごと、もしくは何回か掃除した後に本体のダストボックスを手動で空にする必要があります。本体のゴミを手動で捨てる代わりに、充電ステーションがコンパクトで済み、価格も抑えられます。
水拭き機能を重視するなら「全自動タイプ」がおすすめ
水拭き機能を重視するなら、水拭きモップの給水や洗浄、乾燥機能にも注目しましょう。水拭きモップを取り付けて掃除する別々作業タイプの場合は、掃除後に手動でモップを取り外し、洗浄・乾燥させるといった手入れが必要です。これを怠るとモップに雑菌が繁殖して生乾き臭が発生する場合があります。
モップを手入れする手間を考えると、洗浄や乾燥を行ってくれる全自動タイプがおすすめです。ただしモップの手入れを自動で行うタイプは、掃除用の水と汚水を入れるタンクが必要なため充電ステーションが大きくなるほか、価格も高くなります。
さらに全自動タイプは、温水での水拭きが可能な製品や、洗剤を自動投入してくれる製品、モップを温風や熱風で乾燥してくれる製品など機能はさまざまです。比較検討する際には細かい機能の違いにも着目しましょう。
モップを手入れする手間を考えると、洗浄や乾燥を行ってくれる全自動タイプがおすすめです。ただしモップの手入れを自動で行うタイプは、掃除用の水と汚水を入れるタンクが必要なため充電ステーションが大きくなるほか、価格も高くなります。
さらに全自動タイプは、温水での水拭きが可能な製品や、洗剤を自動投入してくれる製品、モップを温風や熱風で乾燥してくれる製品など機能はさまざまです。比較検討する際には細かい機能の違いにも着目しましょう。

安蔵 靖志
Techジャーナリスト/家電エバンジェリスト
家電製品協会認定 家電製品総合アドバイザー(プラチナグレード)、スマートマスター。AllAbout デジタル・家電ガイド。ビジネス・IT系出版社を経てフリーに。デジタル家電や生活家電に関連する記事を執筆するほか、家電のスペシャリストとしてテレビやラジオ、新聞、雑誌など多数のメディアに出演。KBCラジオ「キャイ~ンの家電ソムリエ」にレギュラー出演するほか、ラジオ番組の家電製品紹介コーナーの商品リサーチ・構成にも携わっている。