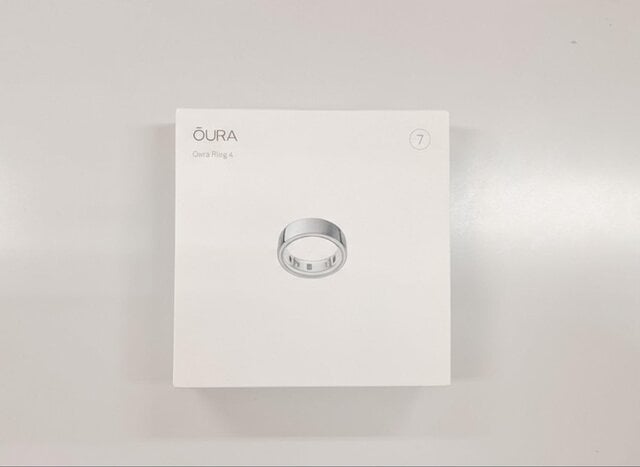これはアートか発明か?“地上最大”のDIYのお祭り「Maker Faire Bay Area 2023」に参加してきた

巨大怪獣カー、炎のアートからメントスコーラまで楽しい作品の数々
非常に多くの出展作品があったが、何個か面白かったものをピックアップして紹介する。

展示の3要素でよく「デカい・光る・音が鳴る」というのがある。この作品はSepia Luxというバルーンでできた怪獣のクルマ。手元のタブレットで目の模様、光るパターンを変えることができる。全長8メートルほどある巨体のヒレが波打って動く。このサイズ感には圧倒された。

こちらはSerenityというファイア・メタルアートだ。炎を吹くので近くに寄ると熱気を感じる。全部で3体いる蜂に似たしっぽから炎が勢いよく吹き出ている。作品の周りに柵のようなものはなく、円形になっている空洞に入っていく子どももいた。

「パワーこそ全て!!」と言わんばかりのクルマがあった。Project Empireという作品で、実際にクルマとして走る。このロケットエンジン調のノズルスカート(本当のロケットエンジンではない)からはスモークが噴出して、ショーを演出していた。

1日目のイベント終了後には“Maker Happy Hour”というパーティが開催される。出展者にビールや食事が振る舞われて、ワイワイするといった感じだ。2019年までのMaker Faire Bay Areaはサンマテオ・イベントセンターで開催されていて、毎年巨大なパエリアが振る舞われるのが恒例となっていた。場所がメア・アイランドに変わった今年、アフター・パーティがあるかどうかが気がかりだったが、今年もばっちりあった。
写真中央にあるのはCelestial Machanicaという太陽系を模した巨大な作品で、実際に回転して動くのを見ると圧巻の一言だ。他にも展示してある作品を見て話しながら飲むビールには格別なものがある(醸造所が会場の横にあって、そこのビールが飲み放題だった)。
写真中央にあるのはCelestial Machanicaという太陽系を模した巨大な作品で、実際に回転して動くのを見ると圧巻の一言だ。他にも展示してある作品を見て話しながら飲むビールには格別なものがある(醸造所が会場の横にあって、そこのビールが飲み放題だった)。

世界中の学校、科学センター、図書館、博物館を地球低軌道にある国際宇宙ステーション(ISS)のライブミッションに接続する、ExoLabという科学実験室の学習ネットワークからの出展もあった。ISSで実際に動いている水循環システムの説明を受けてきた。

「やったらダメ」と言われることほど魅力的なものはない。コーラにメントスを入れると猛烈な勢いで噴き出して、いわゆる「コーラにメントス」「メントスコーラ」と呼ばれるショーになる。102本のコーラにメントスを入れて、濡れたりベトベトになったりするのも構わず、子どもたちが楽しんでいる様子はまさに圧巻だった。
最終日は無念の撤退も、“帰ってきた”Maker Faire Bay Areaを堪能
展示期間は3日間だったが、最後の1日はイベント参加で初めて、途中で撤収して終了した。というのも、会場が吹き抜けの倉庫でとても寒かったのもあって、見事に風邪をひいてしまったからである。

最終日の朝は大雨。風邪をひいたのもあって初の会期中撤退をした
「このまま最終日、出展を続けたら倒れてしまうんじゃ!?」と思い、運営に「風邪をひいたので、ちょっと今日はごめんなさい」と説明して、出展物を片付けてモーテルに帰って寝込んだ。説明しているとき、ちょっと距離を置いて後ずさりされ、パンデミック後だということを実感した。
久しぶりのMaker Faire Bay Areaで最後まで出展できなかったのは非常に残念だったが、2日間の出展で「またMaker Faire Bay Areaが戻ってきた」と強く感じた。
Maker Faire Bay Areaは来年も10月に開催予定とのこと。で、まだ行ったことがない方も、一度は足を運んで参加してみて欲しい。
久しぶりのMaker Faire Bay Areaで最後まで出展できなかったのは非常に残念だったが、2日間の出展で「またMaker Faire Bay Areaが戻ってきた」と強く感じた。
Maker Faire Bay Areaは来年も10月に開催予定とのこと。で、まだ行ったことがない方も、一度は足を運んで参加してみて欲しい。

GMOインターネットグループ 新里祐教
GMOインターネットグループ特命担当プログラマ、デベロッパーエキスパート
先端技術から個人制作・OSS・技術誌での執筆など広く行う。 2019-2020年「IPA 未踏ターゲット ゲート式量子コンピュータ向けソフトウェア開発」、2022年「第25回文化庁メディア芸術祭 エンターテイメント部門 審査委員会推薦作品」、ほかイベントやハッカソンでの受賞など、制作した作品の展示をMaker Faireなどで行っている。